 投稿されたすべての論文が必ずしも出版には至らない、ということは多くの人が理解していることでしょう。しかしジャーナルの数も増えてきているにもかかわらず、すべてが出版されるとは限らない、というのはどういうことなのでしょうか?そのことについて説明してみたいと思います。
投稿されたすべての論文が必ずしも出版には至らない、ということは多くの人が理解していることでしょう。しかしジャーナルの数も増えてきているにもかかわらず、すべてが出版されるとは限らない、というのはどういうことなのでしょうか?そのことについて説明してみたいと思います。
1.出版されるべきでないものは出版されない
残念ながらすべての論文が、出版されなければならないかと言われれば、そうとも限らないのです。
例えば、患者に危害を与える可能性のある論文があります。行ってもいない研究から結果を無理やり作り出す「捏造」、特定の薬剤の効果を強調して害悪は伏せてしまう、「改ざん」などは代表的なものです。
<!–more–>
しかし実際にはこのような捏造や改ざんといった研究不正をはじめから疑うことは難しいでしょう。
研究者一人ひとりの倫理観が試されます。
しかし、やがてはこのような研究不正は、時間が経過すると白日の下にさらされることになります。
研究費の獲得や学位付与、ノルマの達成などの目の前の小さな目標に目を奪われて大局観をなくしてしまった研究者が犯しやすい研究不正です。
このようなことが起こりにくい研究環境を整えることが研究代表や研究施設代表の務めでしょう。
2.論文の雑誌掲載の実情
さて、出版されてしかるべき、という論文であっても掲載されないことがあります。
有名雑誌ともなれば毎日のように論文が投稿されてきます。
投稿された論文が編集者によってその後の査読に回るかどうかを判断されるわけですが、即座にリジェクトされることはそれほど珍しくはありません。
科学的な面白さ(Interest)や新規性(Novelty)に加えて結果が信頼できるかどうか、判断されるのです。
もちろんそのジャーナルが全体として「こういう論文を載せたい」というスコープを持っていますので、そのようなスコープにあっているかを確認することというのは非常に重要です。
そのスコープにあったinterestとnoveltyを備えているか、ということが採択のカギを握っています。
ところで、信頼性についてはどうでしょうか?
研究のデータ品質がきちんと管理されている(データセンターの存在)こと、イベントの評価が論文化に都合よく行われているのではなく、第三者によって評価を受けている、Webサイトで研究の概要を公開している、などは重要です。
論文の中で信頼性を高めることも可能です。方法の部分をきっちりと記載することです。
3.雑誌容量の限界
近年ではオープンアクセスのジャーナルが増えてきていますが、やはり冊子媒体のあるジャーナルは根強い人気を持ちます。
また、長年築いてきた信頼があるのでimpact factorが安定しやすいのも人気の理由の1つでしょう。
しかし、冊子媒体のジャーナルは、掲載できる容量に限度があります。
そのために採択される論文に限度がある、という側面もあります。
ただし、具体的に容量を明記していることはほとんどありません。あくまで舞台裏の話、と捉えていただくのが良いと思います。
4.雑誌に掲載される方法
雑誌に投稿して最終的に採択してもらい、掲載してもらうためにはどうしたらよいでしょうか?
そこには3つの視点が必要です。
- ジャーナルのスコープと合致する内容か
- 科学的に正しい方法で行われたか
- 体裁・必要書類などがすべて整えられているか
前述のように、ジャーナルのスコープに合うような論文を投稿したほうが採択される確率は高まります。
研究の内容だけでなく、研究デザインなどのスタイルもスコープの一部となる場合があります。過去に採択された論文のタイトルや内容に目を通すことをお勧めします。
科学的に正しく実施された研究かどうかは、その記載の厳密さでしか測ることは難しいと思いますが、その道の研究者であれば記載内容をみればその研究のレベルをある程度正しく推測することはできます。
読み手としては結果に目を奪われがちですが、査読においては方法論の確認を念入りに行っていますので、ここも手を抜かずにきちんと記載することが大事です。
最後に、必要な書類や論文としての体裁です。初心者にありがちなのは、論文の内容に集中してしまい、体裁を整えるのをいい加減にしてしまうことです。
これは避けるべきです。さらに、英語を母国語としない場合には英語での記述に慣れておらず、文法上の「軽いミス」も犯している可能性があります。
投稿規定を厳密に読み、それに沿って記載すること、必要とされる書類を早めに準備すること、そして出来上がった論文ドラフトは必ず英文校正に回しておくことなどが肝要です。
このような基本が押さえられない場合には論文をきちんと読んでもらえませんので十分に注意することが重要です。

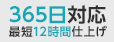
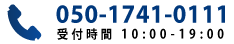
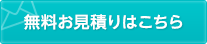
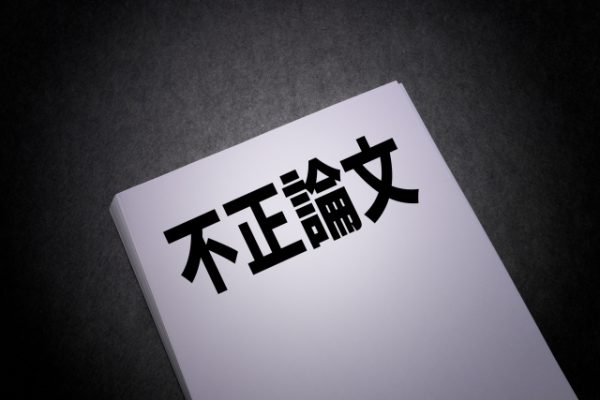 研究成果を論文にまとめる際に、気が付かないうちに「研究不正」を犯している可能性があります。
研究成果を論文にまとめる際に、気が付かないうちに「研究不正」を犯している可能性があります。 近年は研究の内容が高度になってきただけでなく、研究を実施する前の準備段階でも、そして解析を行う段階においても、非常に高度なことを要求されます。
近年は研究の内容が高度になってきただけでなく、研究を実施する前の準備段階でも、そして解析を行う段階においても、非常に高度なことを要求されます。 論文を頑張って投稿したあと、リジェクトされると非常にショックを受けると思います。しばらく立ち直れないことだってあります。
論文を頑張って投稿したあと、リジェクトされると非常にショックを受けると思います。しばらく立ち直れないことだってあります。 論文執筆はとてつもない労力が必要ですが、年間に何十本もの論文執筆をこなす人がいます。そして書き慣れている「達人」たちは、文章が安定していて読みやすいという特徴があります。今回は、そんな論文執筆の達人がどのように上達させてきたかについてのお話をしたいと思います。
論文執筆はとてつもない労力が必要ですが、年間に何十本もの論文執筆をこなす人がいます。そして書き慣れている「達人」たちは、文章が安定していて読みやすいという特徴があります。今回は、そんな論文執筆の達人がどのように上達させてきたかについてのお話をしたいと思います。 研究成果をまとめて論文にまとめる段階では、研究を実施するときはまた異なる難しさに直面します。今回は、研究成果をまとめて世に出す際にやってしまいがちな御法度表現についてまとめてみました。
研究成果をまとめて論文にまとめる段階では、研究を実施するときはまた異なる難しさに直面します。今回は、研究成果をまとめて世に出す際にやってしまいがちな御法度表現についてまとめてみました。 論文を投稿すると、編集部でのチェックを経て査読に回るか、著者に差し戻されるか、即リジェクトを受けるかのいずれかになります。そして、この「即リジェクト」の中には、研究や論文の質以前の問題が含まれています。今回はそのような問題について説明したいと思います。
論文を投稿すると、編集部でのチェックを経て査読に回るか、著者に差し戻されるか、即リジェクトを受けるかのいずれかになります。そして、この「即リジェクト」の中には、研究や論文の質以前の問題が含まれています。今回はそのような問題について説明したいと思います。 論文を書き上げたら、せっかくの成果ですから世の中の人に少しでも知ってもらいたいですね。そこで、自分の論文をどこまで共有できるのか、著作権に問題がないのか、について説明したいと思います。
論文を書き上げたら、せっかくの成果ですから世の中の人に少しでも知ってもらいたいですね。そこで、自分の論文をどこまで共有できるのか、著作権に問題がないのか、について説明したいと思います。 提出された論文を、編集者たちはどのようにチェックして査読に回しているのでしょうか。そして査読結果をうけて編集者としてどのように受理・不受理の判断を下しているのでしょうか?今回は編集者目線で論文のチェックポイントをご紹介してみたいと思います。
提出された論文を、編集者たちはどのようにチェックして査読に回しているのでしょうか。そして査読結果をうけて編集者としてどのように受理・不受理の判断を下しているのでしょうか?今回は編集者目線で論文のチェックポイントをご紹介してみたいと思います。 苦労して書いてきた論文が、ついにアクセプトされ、掲載が決定した後はどのようなプロセスを経ていくのでしょうか。編集部からの連絡をうけてからの流れを説明していきたいと思います。
苦労して書いてきた論文が、ついにアクセプトされ、掲載が決定した後はどのようなプロセスを経ていくのでしょうか。編集部からの連絡をうけてからの流れを説明していきたいと思います。